- 私たちとイヌの出会い・ 他者を愛する能力
- イヌの誕生・旅路の最初の数歩は時のベールに包まれている
- カニス・ルプス・ファミリアリス
- 家畜化と初期の歩み ”オオカミ調教説”
- 家畜化と初期の歩み ”オオカミ自然同居説”
- 異なる2種が互恵関係の中で共存と協力を学ぶ
- 犬種の誕生・全世界で400余りある犬種のほとんどは、ほんの数世紀に生まれたばかり
- 19世紀半ば英国では血統書付きのイヌがステータスシンボルに
- 極端な肉体的特徴によって選択されたイヌは健康問題を抱える恐れがある
- 肉体的特徴によって健康問題を抱える例「フレンチブルドッグ」
- 肉体的特徴と性格の関係性
- 犬の遺伝子疾患と遺伝子検査
- 遺伝子検査を行う意義①犬種に生じやすい遺伝病のリスクの程度を知る
- 遺伝子検査を行う意義②最適なブリーディングを行うため
- 私たち人間を支え続けてくれた犬たちに恩返しするために
私たちとイヌの出会い・ 他者を愛する能力
私たちの祖先がイヌ(当時はオオカミ )を初めて飼いならしたとき、祖先たちがもっていなかったことを想像してみましょう。イヌ以外の家畜、農業、文字、金属の道具・・・。わかっている限り、定住すらしていませんでした。今とは、全く違う暮らし。にもかかわらず、イヌはすでに傍らにいた。
以来、私たちとイヌの生活は、ずっと絡み合ってきたといえます。
オオカミが持つ基本的な体制や社会性、知性、鋭敏な感覚といったものに、様々な肉体的・精神的な特徴を組み合わせて、人間は働き手として、または伴侶として、ふさわしい動物を作り出してきた。今やイヌは、私たち人間にとって得難い伴侶となっている。
近年、イヌの精神活動の解明が進み、いろいろと興味深いことがわかってきた。群れを作る動物としての彼らの習性が、どのように進化してきたか。感情の発達の仕方が、いかに人間のそれと似ているか。他者を愛する能力が、イヌの決定的な特徴かもしれない…。それはなぜか。こうした知見が私たちの理解と付き合い方を変えていくだろう。ペットを可愛がる現代の文化は、何千年もかけて進化してきた人間とイヌの関係における最も新しい段階と言える。イヌが私たちの心と家庭を占める割合が大きくなるにつれ、様々なコトもそれに合わせたモノに変わってきた。
「イヌの飼い主」という代わりに「イヌのパートナー」と呼ぶことができる。イヌが私たちのものであるのと同じくらい、私たちもイヌのものだから。そしてイヌとは何者なのかを深く理解すればするほど、私たちは彼らの愛情と信頼により良く応えることができるのだ。
イヌの誕生・旅路の最初の数歩は時のベールに包まれている
イヌは素晴らしい動物だが、そこに至る進化の旅路もまた同じくらい比類がない。そして旅路の最初の数歩は時のベールに包まれている。オオカミは石器時代の集落のまわりで屍肉を漁っていたのだろうか?それとも、人間の対等なパートナーとして狩りに参加していたのだろうか?疑問は尽きないが、品種改良、特にここ数世紀の品種改良によって、他に類例を見ない肉体的多様性を持つ生物が生み出されたことは間違いない。
カニス・ルプス・ファミリアリス
イヌはもちろん、厳密にいうと「種」ではない。彼らは今でも、カニス・ルプス(タイリクオオカミの学名)の亜種であり、恐竜が絶滅してまもない頃に派生した系統に連なる動物と考えられている。それが証拠にカニス・ルプス・ファミリアリス(イエイヌの学名)には、群れで暮らしたがるなど、依然としてオオカミの特徴が多く残されている。もっとも、イエイヌよりはるかに数で上回る野良犬の群れの習性を見ると、彼らの基本的な性質がいかに変わってしまったかが良くわかる。
生物学的にも、イヌはオオカミの血を色濃く引いている。信じられないほど鋭敏は嗅覚(わたしたち人間にとって視覚情報が欠かせないものであるのと同様、イヌにとっては匂いが欠かせないもの。)発達した聴覚。ある面では人間に勝り、別の面では人間よりも劣る視覚。これらはいずれもオオカミ譲り。ただ、人間を認識したり、人間同士のコミュニケーションを理解したり、人間の気分を察したりする能力は、イヌが独自に発達させたもの。彼らは進化を通じて人類最良の友となった。
家畜化と初期の歩み ”オオカミ調教説”
イエイヌがタイリクオオカミの血を引いていることは科学者の間で意見が一致している。ただ、オオカミの家畜化がいつどこでどのように始まったのかについては、さまざまな議論が交わされている。時期についてはおよそ1万5000年前とする説が有力だが、最近のDNA解析の成果に加え、ベルギーの洞窟で見つかった3万3000年前のものと思われるイヌの頭蓋骨から、最も古い年代に修正される可能性がある。また、近年のさまざまな発見は、オオカミの家畜化が少なくても2回起きたことも示唆している。
最初はヨーロッパで次は東アジアで家畜化され、やがて、ユーラシア大陸の東西を人が行き来するようになると両者の子孫の混血が進んだ。
家畜化がどのように始まったかについては、長らく支持されている説がある。それによると、下記の流れとなる。
ステップ①:野生のオオカミを捕まえて、繁殖させる
ステップ②:生まれた子オオカミの中から最も人懐こい個体を選ぶ
ステップ③:調教する。
ステップ④:狩りに同行させる
確かに、オオカミの鋭い鼻と獲物を追い詰める能力は役に立っただろうが、そうした飼育下繁殖個体の第1世代は、人間が共に仕事をするには、危険すぎたのではないかという異論もある。
家畜化と初期の歩み ”オオカミ自然同居説”
研究者の中には、次のような説を唱える者もいる。
ステップ①:オオカミは初期の集落のはずれで、人間の捨てる残飯を漁っていた
ステップ②:人懐っこいオオカミの方が食べ物にありつける可能性が高い
ステップ③:その中からやがて集落に迎え入れられる個体が出てきた
ただ、この説に対しても、石器時代の人間が捨てた食べ物の量などたかが知れているため、同説は到底成り立たないという反論がなされている。
異なる2種が互恵関係の中で共存と協力を学ぶ
上記に記述した説より、オオカミたちはただでありつける食べ物目当てに集落のまわりをうろつくのではなく、対等の相手として原野で人間に出会ったのではないか。異なる2つの種が互恵関係の中で共存と協力を学んだ。オオカミを飼いならすことができたとしたら、そういう前段階を経ているはず。あるいは、ひょっとしたら残飯説が正解なのかもしれない。残飯を漁るうちに人間に心を許すオオカミが出てきてその一部が人間との狩りに同行するようになっとと考えられなくもない。
オオカミがどのように飼いならされたか、正解なところは誰にもわからないが、彼らの高度な社会性と忠誠心は、人間と驚くべき和合を果たす土台となった。
犬種の誕生・全世界で400余りある犬種のほとんどは、ほんの数世紀に生まれたばかり
ほかよりも人懐こいオオカミを数頭手なずけてから、繁殖のコントロールに至るまで、おそらく長くはかからなかっただろう。私たちの祖先は狩猟、護衛、牧畜にそれぞれ最も適した個体を選び出し、世代を重ねることで、その特性に磨きをかけていった。
重要視されたのはイヌの実用性であって、外見ではなかっただろう。外見の改良が始まるのはのちのことだ。もっとも、中身に外見がついてくることもある。たとえば、5000年前の壁画にはマスティフに似た大型犬とほっそりした犬が描かれているが、恐らく前者は番犬として、後者は猟犬として使われたと思われる。
こうした犬種がその後どうなったかはもはや知る由もないが、その類型は今でも見分けがつく。
一部、ヨーロッパに起源をたどるものもあるが、今の犬種の大半は過去数世紀以内に開発されている。多種多様な獣猟犬、鳥猟犬、テリア、牧畜犬が出現したのは16世紀のことだ。そこでもやはり実用性が重視されている。たとえば18世紀の英国では、肉を柔らかくするという思い込みから家畜の殺傷を犬の群れに任せていたが、雄ウシ(ブル)に怯まず飛びかかってゆくイヌはどんなイヌでもブルドッグとされた。ずんぐりした体つきの、あごの強いイヌが好まれたというのは、副次的な結果に過ぎない。
19世紀半ば、イヌがビクトリア朝期英国の上昇志向が強い中産階級のステータスシンボルになるにつれて、人々の好みは劇的に変わる。外見がかつてないほど重視されるようになった。もちろんシンボルにとどまらず、飼いイヌは家族の一員となった。イヌを一種の「代弁者」になぞらえる歴史学者もいた。人間関係を取り持ち、お堅いビクトリア朝時代の人々がはっきり口にするのをためらうような気持ちを表現するのにつかわれているのだと。
19世紀半ば英国では血統書付きのイヌがステータスシンボルに
具体的には、定義された体形と一致していることが、中身の保証になった。例えば、グレイハウンドがほっそりとした体つきをしているのは、単なる傾向だったが、それがやたらとありがたがあれるようになった。
またフォックステリアの頭は平らで狭くなければならなかったが、狭すぎても駄目だった。被毛がなめらかか荒いかによって犬種の定義自体が変わることもありえた。
現在の犬種のほとんどは、このように開発されたのだ。
極端な肉体的特徴によって選択されたイヌは健康問題を抱える恐れがある
現在、認知されている犬種の数は全世界で400を超えるが、体形、体格、能力は千差万別。同一種の中で多様性に関してイヌに勝る動物はいない。試しに、チワワとセントバーナードが並んでいるところを想像してみてほしい。人間でいえば、中肉中背の人が、体重3トンの巨漢と並んでいるようなもの。
ただし、体形にこだわりすぎるのも問題。原型となる数頭の個体から増やしたい犬種の遺伝子プールは非常に小さなものになり、それは遺伝的欠損が生じる確率が高いことを意味する。極端な肉体的特徴によって選択されたイヌは健康問題を抱える恐れがあるのだ。
肉体的特徴によって健康問題を抱える例「フレンチブルドッグ」
たとえば、フレンチブルドッグ
①鼻が短いことで、呼吸器障害を患いがち
②飛び出した目はけがをしやすい
もちろん、さらなる改良によって解決できる問題もあるが、純血種のイヌを飼うことは、多くの人にとって以前ほど重要ではなくなっている。雑種犬(ミックス犬)もまた、純血のイヌと同じように特別だからだ。とは言え、犬種にこだわる人が多いのも事実だ。
肉体的特徴と性格の関係性
肉体的な特徴は犬種によってさまざまに異なるものの、性格がどの程度まで犬種に左右されるかについては、驚くほど盛んな議論が交わされている。たしかに、いくつかの性質は、犬種に付随する傾向がある。たとえば、ラブラドールレトリバーは他の犬種よりも好奇心が強く社会性に富むことが経験的にわかっている。しかし、環境が大きな役割を演じていることも否定できない。犬種間の違いよりも個体間の違いのほうが多様がと主張する研究者もいる。言い換えれば、血筋はどうあれ、イヌは1匹1匹違うのだ。
犬の遺伝子疾患と遺伝子検査
現在のイヌ、特に日本において、体形及び容姿にこだわりすぎる問題が表面化している。 先に述べた通り、 原型となる数頭の個体から増やしたい犬種の遺伝子プールは非常に小さなものになり、それは遺伝的欠損が生じる確率が高いことを意味する。極端な肉体的特徴によって選択されたイヌは健康問題を抱える恐れがある。特にビジネス先行型の日本の悪徳ブリーダー及びそれに連なる大手を含む生体販売店の結託によって量産された「誤った交配」による遺伝子疾患、「生育環境が劣悪」による寄生虫感染などが挙げられる。更に、日本の場合、無責任による飼育放棄。保護センターからの引き取りによる、性格な犬種情報の把握(特にミックス犬)が困難。これは、後々、発症することが予想され未然に防ぐことができたかもしれない、遺伝性疾患のリスクを大きく抱える事を意味する。
犬の遺伝子疾患に関しての事例や説明は、更に長文となるため、割愛させて頂く。
遺伝子検査を行う意義①犬種に生じやすい遺伝病のリスクの程度を知る
その犬種に生じやすい遺伝病のリスクの程度を知ることで、飼い主がその犬と暮らしていくうえでの備えにしてもらおうというものである。事前に病気の知識があれば、定期検診を行うとともに、万が一発症したとしても、早期に症状を発見することができるだろう。それは重症化の予防にもつながる。
遺伝子検査を行う意義②最適なブリーディングを行うため
最適なブリーディングを行うためである。遺伝病は、父犬・母犬の両方またはどちらかからその遺伝子を受け継ぐことで、次世代に伝わっていく。あらかじめ父犬と母犬それぞれの遺伝病のリスクがわかっていれば、病気の子が生まれないような交配の組み合わせを選択することが可能なのである。
私たち人間を支え続けてくれた犬たちに恩返しするために
WEBで結果確認可能な犬の遺伝子検査【Pontely】もちろん、「遺伝病を無くす」というのは簡単なことではない。当然お金もかかるし、時間もかかる。また、単純にクリア同士のブリーディングを行えばいいという話でもない。それによって、新たな遺伝病が生じるなど、別の歪みが生じてしまうおそれもある。慎重な判断と検証が求められるのだ。それでもこの先、100年後も200年後も、私たち人間がこの「犬」という素晴らしい生き物とより豊かな関係を構築していくために、そして数百を超える世界中のさまざまな犬種を健全な形で継承していくためには、どこかで遺伝病と向き合わなくてはならない。それが今この時であるということも、また間違いないだろう。愛すべきパートナーとして、ずっと私たち人間を支え続けてくれた犬たちに恩返しするために。犬を取り巻くすべての人々が取り組むべき課題なのである。
今、最先端の遺伝子検査をペットにも採用する流れが海外で広まっている。検査キットで簡単にDNAデータから健康リスクを知ることができる現在。ぜひペットと暮らす未来のために、パートナーである愛犬に遺伝子検査を始めてみてください。
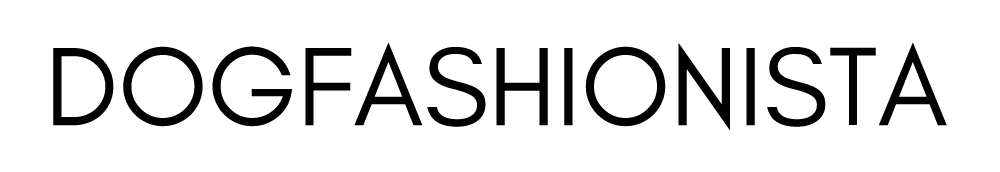

コメント